こんにちは、
元消防士YouTuberのKIYOYUです。
今回は火災原因調査の中でも、
警察との合同調査の流れについて
確認していきます。
外部の組織と協力して動くので
注意点、配慮すべき点などが
いくつかあります。
警察と目的の相違
警察と消防では目的に違いがあります。
消防→消防予防業務のため

消防法第35条の3の2
双方、目的に違いはありますが、
調査は協力することが
法的にも定められています。
警察との相互連絡
火災発生後、
合同鑑識をやる場合には
警察、消防の
各責任者(担当者)同士で
連絡をとりあい、
鑑識開始時間などを取り決め
各々、現地に向かうことになります。
現場に到着しすぐやること
作業開始前に
消火活動後に現場に到着したとき
私の場合、
まず最初に建物の外周の写真を
東西南北から撮ってしまいます。
後で警察の車両が来てしまったりと、
落ち着いて撮影できるタイミングは
作業前だと考えるためです。
到着時のシチュエーション
上記の内容で、
到着してすぐ写真を撮った方が良い
と述べましたが、
それは到着時の
シチュエーションにもよります。
警察が先着して
既に作業に入っている場合もあります。
また、鎮火前に現着した場合は、
消防隊がまだ消火活動をしており、
活動の妨げになってはいけません。

この場合は可能な範囲で
写真を撮ったり、
先に建物の関係者や、
民家なら近隣の住民に
事情聴取をするなどして
鎮火を待ちます。
基本は警察と足並みを揃える
事情聴取時の注意点
警察側が、
出火建物の関係者などと
すでに接触していた場合は
すぐ合流すべきです。
氏名、住所、職業などの情報を
関係者から免許証を見せてもらいながら、
控え始めていることがあります。
関係者側も、
何度も同じ話をしたくはありません。
内心では
「警察の次は消防かー、面倒くさい」
と思っているかもしれません。
火災に遭ってしまい
落胆している場合もあります。
関係者側の気持ちを
配慮した活動も、
時には必要ですので、
警察と同じタイミングで
聴取できる情報は
一括して
聴取してしまいましょう。
日を跨ぐ場合でも「鉄は熱いうちに打て!」
火災が深夜に発生する場合もあります。
火災はいつ起こるか分かりません。
そんな時、
関係者とどうしても
接触できないこともありますし、
接触できても、相手の都合上
事情聴取できないこともあります。
最低限の話を聞けたとしても、
後日、再度同じ質問をしたときに、
違った回答が返ってくることもあります。
私が消防士だったとき、
上司が「この前言ってたことと違うよー、
チクショーっ!」とボヤいていることもありましたが、
私は「早く聞かない方も悪いんじゃないか?!」
とも思いました。
さすがに誰しも人間なので、
記憶が曖昧になってしまう事は
多々あります。
日数が経ってしまえば、
経ってしまうほど、
尚更です。
質問調書は否定の材料になる
重要な書類なので、
関係者から得たい回答は
必ず速攻で得るように
心がけましょう。
また警察と合同で事情聴取した場合、
双方の内容に食い違いがあっては
いけませんので、
内容の統一性を持たせるように
下話をしておきます。
写真撮影時の注意点
火災調査で使う写真は
現場の様子を読み手に
ストレートに伝えるものです。
もし、火災調査で
写真撮影の担当になった場合は、
写真撮影だけに専念しましょう。

残渣物を掘り起こす作業は
他の隊員に任せます。
手が汚れてしまうと
撮影に支障をきたします。
特に警察との合同調査では、
警察と消防の複数人で
残渣物を掘り起こします。
出火箇所とおぼしき箇所は、
掘り起こすプロセスで
段階的に撮影をします。
①掘り起こす前
②掘り起こした後
③水で濯ぎ流し床面を確認
まずは掘り起こす前に
警察と同時に写真を撮ります。
この後は、基本的には
流れに身を任せて、
「写真撮りまーす」のタイミングで
警察と消防が同じタイミングで
写真を撮りながら、
作業が流れていきます。
警察側も、お互いに写真が必要だと
理解してくれているので、
発掘後にも手を止めて
撮影タイムをちゃんと
設けてくれます。
そして、発掘後には
バケツに水を汲んできて
例えばフローリングの
焼損箇所を
水で濯ぎ流すことで、
よりはっきりと床面全体を
確認することも
あります。
もちろん濯ぎ終わった
そのタイミングでも
写真を警察と一緒に
撮ります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
警察と消防は相互に協力し、
それぞれの目的に向かって
火災原因調査を進めます。

お互いにより良い調査ができるよう、
配慮し合い、
不備のない書類の作成に
つなげることが大切です。
今後調査に携わる人は、
ぜひ参考にして、
業務時に意識してみてください。


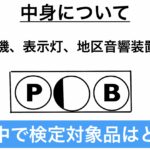
コメント